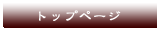|


あのひとの きもの姿見てみたい・・・と思いませんか?
きものデビューしてみませんか?
きものほど、男の格を上げるおしゃれはありません。
|


| 着物 鼠色縦縞 お召し【丹後ちりめん 】 AB反 と 羽織 憲法色 無地紬【絹100%】 角帯・羽織紐のセット |
|
|
| 詳細説明 |
鼠色地に茶系の細い縦しまが入ったお召しです。
お召しならではの絹の光沢と、さらっとした手触りが特徴です。
糸を先に染める先染めのきものは、織りのきものと言われ一般的には普段着とされています。
その中でお召しは、織りのきものでありながら江戸時代には、礼装として扱われていました。
武士が、登城するときには、お召し着用となっていたようです。
現在のサラリーマンに置き換えると、スーツにあたるものでした。
丈夫でしわに成りにくいお召しを着る事は、とても合理的だったのです。
一尺五分(約40cm)の生地巾があります。
男性の方のサイズに十分対応できる生地巾です。
男物のきものは、モノトーンのきものを選びがちですが、
一味違う茶系のコーディネイトを楽しんでみてはいかがでしょうか?
羽織…渋い茶系の紬です。
「茶」と言う色に特別な思いを抱いていた時代がありました。
江戸時代[17世紀始めごろまで]江戸の染色は、藍を染める紺屋(こうや)と茶を中心に染める茶染屋が行っていました。
その頃茶染めの技法は、秘伝とされていました。
それまできものの染色には、使用されていなかった茶。
小袖などに染められた茶は、江戸の人々にとって新しい色で大人気となりました。
17世紀中ごろ、茶染め人気もあり茶染めの技法書が出版され急速に広まっていきました。
江戸後期には、流行の最先端を行く歌舞伎役者がこぞって茶染を愛用しました。
歌舞伎役者にちなんだ芝翫茶(しかんちゃ)・路考茶(ろこうちゃ)等の色名が付いています。
男物の紬として織られていますので、生地巾が広く1尺一寸(約41.8cm)あります。
体格の良い方はもちろん、きものより少し大きめに仕立てる羽織などにお勧めです。
江戸の人々が愛した茶染めを、楽しんでみて下さい。
羽織ひもマグネット式で、中央の玉の部分が、マグネットになっていて簡単に取り外しができます。
角帯米沢織り 4,1m
◇お仕立・パールトーン加工他はお仕立についてをご覧ください。
◆ご購入に際して、詳細やご不明な点、注文できない場合は、お問い合せフォーム、
又は、電話でお気軽にお問い合せ下さい。 |
| ネット価格 |
119,800円 (きもの・羽織・角帯・羽織紐)
199,800円 《着物手縫い(胴裏付)・羽織手縫い(額裏付)・角帯・羽織紐》
|
|
|
|
COPYRIGHT(C)2009 株式会社とまり ALL RIGHTS RESERVED.
|
|